仏教で考える毒親
仏教には
雑毒の善(ぞうどくのぜん)という言葉があります
いいことをしているんだけれど、
その根性が煩悩から生まれているので
見返りを求める行いをいいます
こちら側から何かいいことをして
それ相当のお返しが帰ってきたら気持ちがいいのですが、
そうでなかった場合は
「あれをしてあげたのに」の“のに”がついてしまう
それは毒が混じっているわけです
煩悩というのは毒なんですね
これを親が我が子に対する思いで考えてみますと
毒が混じっていると
「あんたのために私はどれだけ苦労して育ててあげたと思っているの!」
という思いが沸き起こります
その心は執着という煩悩からです
相手をコントロールしたいという愛着です
これを自分で気づくかどうかになります
『父母恩重経』というお経は
親の恩愛の深さについてのお釈迦さまの言葉です
(私はお通夜の時に唱えています)
親の恩は10あり
親は子どもが大人になるまですべてを犠牲にして育てるという内容
しかし、
子どもが結婚すると一変し、親に尻をむけるような態度になる
自分たちだけの空間でイチャイチャ、親と会いたいと思うことはなく
会話をしようとも思わなくなる
「ねえ、ちょっとこれをして、(手伝って)」と頼んでも、
「なんで?自分でやったら?」と10回に1回しか答えてくれない
孫もまたそれを聞いているから、祖父母を疎んじ、
その配偶者も同様に年老いた父母を放置するようになる
なんでこういう大人になってしまったんだろうか
それならいっそ、産まなければよかったという思いが出てくる
と『父母恩重経』の中でお釈迦様が説かれています
年をとると子どもだけが頼りになり
その執着心がとてつもなく大きくなり
愛別離苦、手塩に育てた我が子と距離が離れていく苦しみ
求不得苦、自分の願いを聞いてくれない苦しみが
襲ってくるようになる
一生懸命であればあるほどその苦しみは強くなります
仏教では
この世というものは「火に包まれたの家に住んでいるもの」といいます
すべて燃えてなくなる不安だらけということです
世間虚仮 唯仏是真
本当のものはひとつもない、聖なるものへのあこがれる必要
子どもは大きな幸せの存在であるけれど、
いつかは離れてしまう無常なるもの
財産や地位、名声などと一緒です
いつまでも自分を幸せにするものはではないから
どこかで区切りをつける必要があるわけです
・。*・。*・。・。*・。*・。 【円相寺副住職のイベント情報】 ・。*・。*・。・。*・。*・。 【令和8年秋完成】 円相寺第2納骨堂加入者先行予約受付中 【毎週土曜】朝7:00 一緒にお祈り(お経を読むお参り)しませんか? 【第1、第3土曜】19:30~21:00「寺ヨガ」 【毎週金曜】15時~17時 大人のための書道教室(美和台公民館) 【満員お礼】小中学生対象リアル寺子屋式子ども書道教室はこちら ↓↓↓円相寺副住職のイベント情報公式LINE@ LINEでご連絡とられたい方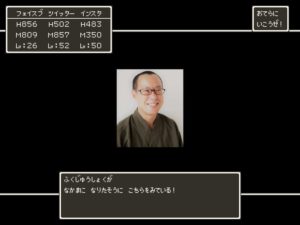 副住職が仲間になりたそうにこちらを見ている!
【お問い合わせ】
円相寺副住職 裏辻正之(えんそうじ ふくじゅうしょく うらつじ まさし)
アイコンをポチると各SNSをご覧になれます↓↓↓
副住職が仲間になりたそうにこちらを見ている!
【お問い合わせ】
円相寺副住職 裏辻正之(えんそうじ ふくじゅうしょく うらつじ まさし)
アイコンをポチると各SNSをご覧になれます↓↓↓



