お盆供養は施餓鬼供養、なぜ七夕は「たなばた」と読むのか?
子どものことを「ガキ」といいますが
これは仏教の餓鬼(がき)から来ています
常に自分の欲望を満したくて泣き喚いている姿
身長100センチ程
目はギラギラ、
髪の毛薄らハゲ
ガリガリ(我利我利)に痩せていて
爪はナイフのように長く鋭い
喉は針の穴より小さく
水や食べ物を食べようとすると口から炎が出て
顔面に火傷を負っている
痩せている状態を「ガリガリ」といいますが、
餓鬼が常に自分だけが他人のものまでも掻き取るように求めるということから
「我利我利」と言われ、そこから
餓鬼の見た目がひどく痩せているために
ひどく痩せている状態を「ガリガリ」と言われるようになったそうです
(円相寺では)
お盆はこの餓鬼を供養するための特殊なお経を読み上げ
餓鬼を供養し、次の世では人として生まれ
仏道を歩むように願います
また、
その餓鬼を救った功徳(五福)とお念仏の功徳でご先祖さまを供養します
お檀家さんのご自宅では
お寺で作った五色の短冊(略したもの)を仏壇にかけてもらいます
この短冊にはお経の一説や如来様のお名前が書かれており
餓鬼を供養するための依代にするためです
円相寺では7月の中旬に
施餓鬼供養のための“棚”を出して
施餓鬼供養のために“幡”をかけてお施餓鬼法要を行います
これから8月15日までお盆として
とりわけ初盆の方の卒塔婆供養と
その前準備と心構えをお伝えします

おそらく、私が思うに
七夕(たなばた)とは「棚幡」のことであり
棚とは施餓鬼供養のための棚で
幡とは五色の短冊のことであると予想します
(七夕の歌の歌詞に五色の短冊が出てきます)
お坊さんがその短冊に字を書いて餓鬼を供養し五福というご利益を私たちに振り向けました、そういう現世利益を求めるところから、いつしか願い事を書くようになったと思います

なぜ“七”なのか、
ご先祖さまが帰られるお正月とお盆
七日正月といわれるように1週間という節目であるため
七日間のお盆、つまり七夕になったと思います
正月は朝、お盆は夕方に行います
この夕方に餓鬼が現れるそうです
また、
七夕は7月に行う地域もあれば
8月に行う地域もあり
お盆もまた然りです
寂しいお盆になるところもあると思います
いつも以上に賑やかに
美味しいものを囲んで亡き方の思い出話をするのは
とてもいい供養になるのでは
合掌
南無阿弥陀仏
・。*・。*・。・。*・。*・。 【円相寺副住職のイベント情報】 ・。*・。*・。・。*・。*・。 【令和8年秋完成】 円相寺第2納骨堂加入者先行予約受付中 【毎週土曜】朝7:00 一緒にお祈り(お経を読むお参り)しませんか? 【第1、第3土曜】19:30~21:00「寺ヨガ」 【毎週金曜】15時~17時 大人のための書道教室(美和台公民館) 【満員お礼】小中学生対象リアル寺子屋式子ども書道教室はこちら ↓↓↓円相寺副住職のイベント情報公式LINE@ LINEでご連絡とられたい方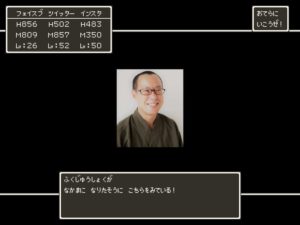 副住職が仲間になりたそうにこちらを見ている!
【お問い合わせ】
円相寺副住職 裏辻正之(えんそうじ ふくじゅうしょく うらつじ まさし)
アイコンをポチると各SNSをご覧になれます↓↓↓
副住職が仲間になりたそうにこちらを見ている!
【お問い合わせ】
円相寺副住職 裏辻正之(えんそうじ ふくじゅうしょく うらつじ まさし)
アイコンをポチると各SNSをご覧になれます↓↓↓




